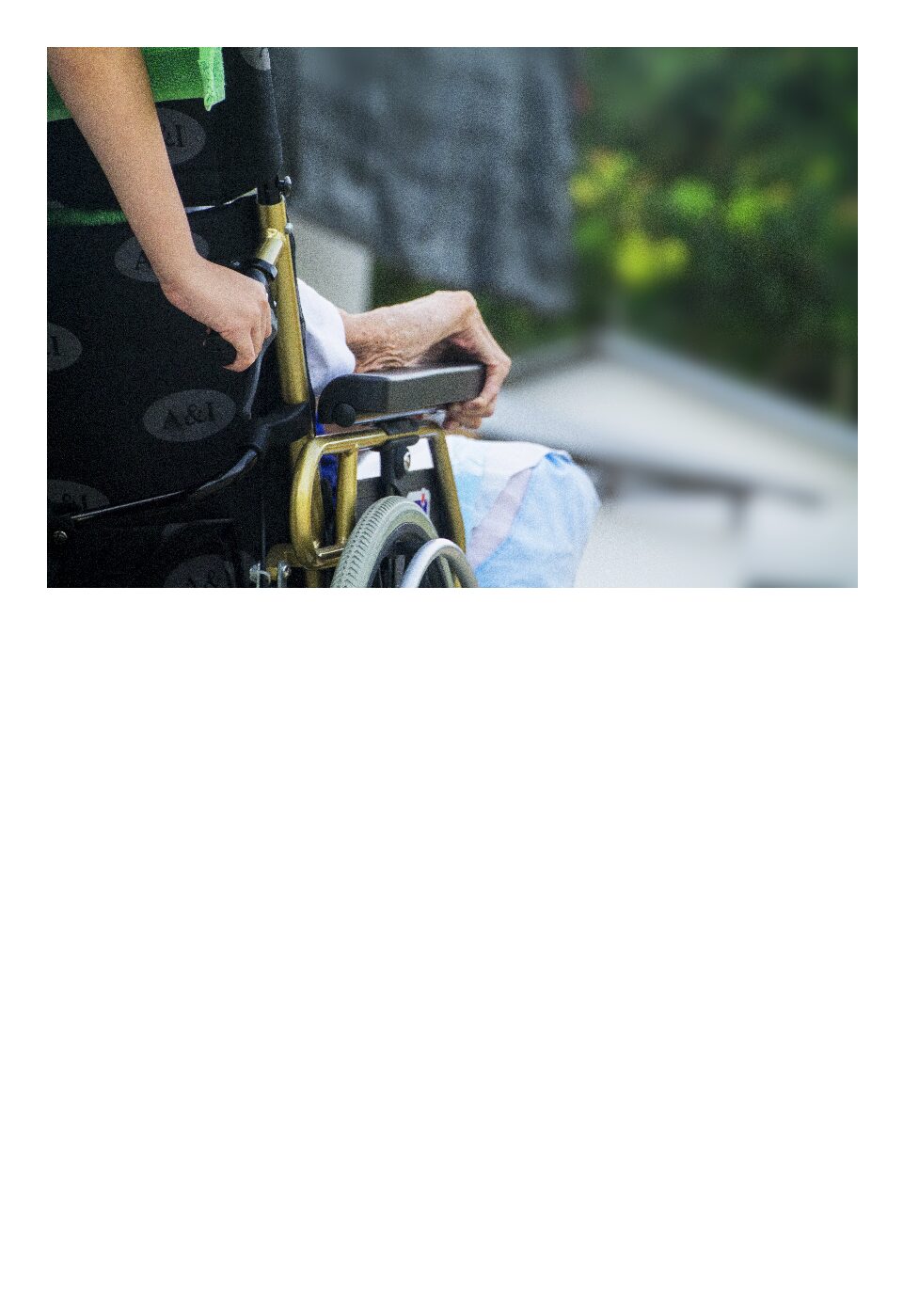わかりやすく解説していきますので、是非ご参考にしてください。
無資格・未経験でも働ける職種
生活支援員
場合によっては、金銭の管理も行い、相談やアドバイスをしていきます。
・働ける場所
グループホーム
生活介護事業所
就労継続支援A型・B型事業所
就労移行支援事業所
障害者支援施設(多機能型施設)
社会福祉協議会
職業指導員
・働ける場所
就労継続支援A型・B型事業所
就労移行支援事業所
職業指導を実施する児童福祉施設
世話人
グループホームに住む方の日常生活面のサポート(洗濯、掃除、調理等)、相談業務、金銭管理等を行います。
・働ける場所
外部サービス利用型グループホーム
介護サービス包括型グループホーム
サテライト型住居
就労支援員
・働ける場所
就労移行支援事業所
指導員
・働ける場所
放課後等デイサービス
児童発達支援センター
重度心身障がい児を対象とした児童発達支援事業
資格・経験が必要な職種
社会福祉士(国家資格)
障がいを持つ方、高齢者の方に専門的知識、技術をもって相談に応じ、助言・指導と福祉サービス提供事業所、医師その他の保健医療サービス、その他の関係者の連絡及び調整その他の援助を行います。
障がい者支援だけでなく、高齢者施設、医療施設、地域の福祉関係施設、市町村役場等幅広く働ける職種があります。
・資格取得方法
福祉系4年生大学卒業者(指定科目履修)、社会福祉士指定養成施設卒業者等で、社会福祉士国家試験に合格し登録することが必要です。
・主に働ける場所
高齢者施設
障がい者支援施設
児童福祉施設
児童相談所
社会福祉協議会
地域包括支援センター
学校・学童
医療機関
介護福祉士(国家資格)
障がいを持つ方、高齢者の方に心身の状況に応じた介護を行います。具体的には、食事介助、入浴介助、排泄介助、更衣介助等の身体介護と日常生活を送る上で必要な洗濯、食事の支度、掃除、買い物代行等の生活援助を行います。介護業務全般の仕事が行えるので、幅広く職場を探す事が可能です。
・資格取得方法
①3年以上の介護等の業務に関する実務経験及び都道府県知事が指定する実務者研修等における必要な知識及び技能の習得を得た後に、国家試験に合格して取得する方法
②都道府県知事が指定する介護福祉士養成施設等において必要な知識及び技能の習得を得た後に、国家試験に合格して取得する方法
③文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定する福祉系高校において必要な知識及び技能を取得した後に、国家試験に合格して取得する方法
・主に働ける場所
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
介護付き有料老人ホーム
デイサービス
グループホーム
訪問介護事業所
居宅介護・重度訪問介護事業所
移動支援事業所
生活介護事業所
就労継続支援A型事業所
就労継続支援B型事業所
就労移行支援事業所
地域活動支援センター
小規模作業所
社協
福祉(系)生協
精神保健福祉士(国家資格)
精神に障がいがある方に対して相談援助業務を行います。地域相談支援の利用に関する相談や社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応ために必要な訓練、その他の援助を行います。具体的には、病院などでは、入退院の間の問題の解決をめざし、関係機関との連絡調整、患者や家族との面接等を行い、社会生活に適応できるように援助します。働く場所は多岐にわたり、仕事内容も職場によって変わってきます。
・資格取得方法
①保健福祉系大学等を4年・指定科目を履修して国家試験を受験して合格する
②保健福祉系短大等を3年・指定科目を履修してから相談援助実務1年を経て国家試験を受験して 合格する
③保健福祉系短大等を2年・指定科目を履修してから相談援助実務2年を経て国家試験を受験して合格する
④福祉系大学等を4年・基礎科目を履修後、短期養成施設等(6ヵ月以上)での履修を経て国家試験を受験して合格する
⑤福祉系短大等を3年・基礎科目を履修後、相談援助実務1年と短期養成施設等(6ヵ月以上)での履修を経て国家試験を受験して合格する
⑥福祉系短大等2年・基礎科目を履修後、相談援助実務2年と短期養成施設等(6ヵ月以上)での履修を経て国家試験を受験して合格する
⑦社会福祉士資格保有者、短期養成施設等(6ヵ月以上)での履修を経て国家試験を受験して合格する
⑧一般大学4年、一般養成施設(1年以上)での履修を経て国家試験を受験して合格する
⑨一般大学3年、相談援助実務1年と一般養成施設(1年以上)での履修を経て国家試験を受験して合格する
⑩一般短大等2年、相談援助実務2年と一般養成施設(1年以上)での履修を経て国家試験を受験して合格する
⑪相談援助実務4年、一般養成施設(1年以上)での履修を経て国家試験を受験して合格する
・主に働ける場所
精神科病院
精神病床、精神科、心療内科を広告している病院や診療所
保健所
保健センター
精神保健福祉センター
就労継続支援事業所
グループホーム
地域活動支援センター
福祉ホーム
社協
福祉事務所
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者
障害福祉サービスを利用される方に適切なケアが提供できるように、個別支援計画を作成し、提供するサービスの内容の管理、関係機関との連絡調整、職員の育成等を行います。サービス管理責任者になるためには、実務での経験と研修が必要になります。
・資格取得方法
保有資格や業務によって変わってきます。
<実務経験>→実務経験1年あたり、勤務日数が180日の実績が必要になります
①相談支援業務を5年従事
②直接支援業務を8年従事
③直接支援業務(資格ありの場合)を5年従事
④相談支援業務又は直接支援業務(国家資格等保有者)を3年従事
※③の資格…社会福祉主事任用、介護職員初任者研修、児童指導員任用、保育士、精神障害者社会復帰施設指導員任用等
④の資格…医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、精神保健福祉士、栄養士、管理栄養士
<研修>
実務経験を満たした方は、サービス管理責任者等基礎研修の受講が可能となり、終えると「基礎研修修了者」となります。その後、基礎研修修了者としてOJT期間を2年積んだ後は、サービス管理責任者等実践研修を受講し正式にサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)としての配置が可能になり、その後、5年に1度のタイミングでサービス管理責任者等更新研修の受講が必要です。
・主に働ける場所
生活介護
ケアホーム
療養介護
施設入所支援
グループホーム
宿泊型自立訓練
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
放課後等デイサービス
児童発達支援
医療型児童発達支援
保育所等訪問支援
障がい児入所支援施設等
相談支援専門員
障がいがある方とその家族の相談を受け、自立した日常生活、社会生活を営む事ができるよう、障害福祉サービスの利用計画案の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、子どもから大人まで全般的な相談の支援を行います。
・資格取得方法
保有資格や業務内容によって変わってきます。
<実務経験>
相談支援業務に携わっている場合
①2006年9月30日以前に次に上げる業務に通算3年以上従事し2006年10月1日時点で従事されていた方
・障がい児相談支援事業
・身体障がい者相談支援事業
・知的障がい者相談支援事業
・精神障がい者地域生活支援センター
②医療機関において相談支援業務に5年以上従事する方で次に上げるいづれかに該当する方
・社会福祉主事任用資格を有している
・介護職員初任者研修(訪問介護員2級以上)の研修を修了している
・医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、社会福祉士、介護福祉士などの国家資格等を有している
・施設での相談支援業務の従事期間が1年以上ある
③就労支援に関する相談支援業務に5年以上従事する方
④特別支援教育において進路相談・教育相談の業務に5年以上従事する方
⑤都道府県知事が認めた業務に5年以上従事する方
介護業務に携わっている場合
①医療機関及び施設において介護業務に10年以上従事する方
②都道府県知事が認めた業務に10年以上従事する方
有資格者の場合
①社会福祉主事任用資格者、保育士、児童指導員任用資格者、介護職員初任者研修(訪問介護員2級以上)修了者等の方は5年の実務経験が必要
②相談支援・介護等の仕事をしていて医師や看護師、准看護師、社会福祉士など国家資格が必要な業務期間が5年以上ある方は3年以上の実務経験が必要
<研修>
実務経験を満たした方は、相談支援専門員として働くための知識や技術を習得するため、各都道府県で行われる相談支援従事者初任者研修の受講が可能です。42.5時間の講義・演習に加えて2ヵ月間の実習を要します。研修の日数、カリキュラムは地域によってことなります。研修修了者は、相談支援専門員としての配置が可能になりますが、5年ごとの資格の更新が必要です。
その際、相談支援従事者現任者研修の受講が必要です。
・主に働ける場所
一般相談支援事業所
特定相談支援事業所
障がい児相談支援事業所